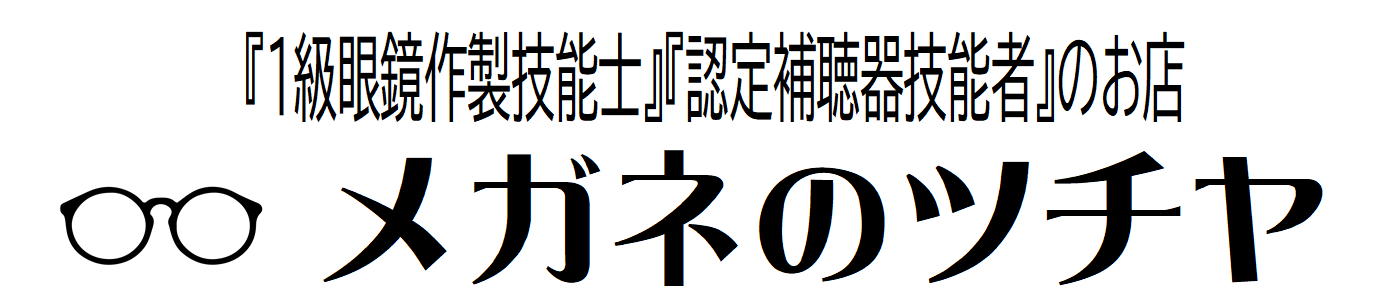難聴と認知症の関係
平成27年に厚生労働省から「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」が発表されました。その中で発祥の危険因子の一つとして加齢、遺伝性のもの、高血圧、糖尿病、喫煙、頭部外傷と並び「難聴」が挙げられてから、補聴器の使用と認知症の関係が注目されています。
また世界的に権威のある医学雑誌ランセットが2020年に掲載した記事でも、認知症の研究が進み、認知症のリスク要因のうち40%に当たる12個の因子がわかってきた、そのうちの一つが難聴であると述べられています
『ランセット』(英語: The Lancet)は、週刊で刊行される査読制の医学雑誌である。同誌は世界で最もよく知られ、最も評価の高い世界五大医学雑誌の一つであり、編集室をロンドンとニューヨーク市に持つ。
Wikpedia

(認定補聴器技能者)
認定補聴器技能者として聞こえに悩みを抱えた方とお話をしていても、耳が聞こえにくくなったことで友人の話が理解できず、人に会うのが億劫になり自宅に閉じこもり気味になってしまうことはよくあります。
そうした方々が補聴器を付けることでまた積極的に外出できるようになり、家族以外の人に会ったり、様々なところに行くことが刺激になっているということは理解できます。

(
補聴器を付けるのは人と話すときだけという方もいますが、私はご自宅で一人でいるときにも極力つけていただくように指導しています。
補聴器を付けていないときには聞こえ無い蝉や鳥の鳴き声、前を通る通学中の小学生のはしゃぎ声、救急車のサイレン、エアコンの運転音これらの環境音も聞いていただくことが刺激になると考えるからです。
今まで聞こえなかった音が入ってきてうるさいと感じる方もいらっしゃいますが難聴になる前は聞こえていた音ですので我慢にならない程度で聞いていただけたらと思います。
参考リンク
認知症と難聴(慶応義塾大学医学部耳鼻咽喉科 教授 小川郁 先生監修)
GNリサウンドウェブサイト
「これって難聴かも?」
- 聴力が低下することで自分の声も聞きづらいため、話し声が大きくなってしまい「怒っているみたい」と言われる
- 友人に「話しかけても無視された」と言われる
- お互いに話すことが億劫になることで会話の量が必要最低限に減り、「会話が楽しくない」と感じる
- 「テレビの音が大きすぎる」と家族に指摘される
当てはまる方は認定補聴器技能者が常駐する当店にご相談ください。
また必要があれば補聴器相談医の先生へのご紹介もいたします。